はじめに
日本の都市は「東京」と「その他」に大きく分けられます。
そして「その他の都市」も人口規模によって、仕事の数・時給・交通のあり方・生活設計が大きく変わります。
私は福島市で暮らしながら、その違いを日々実感しています。
そこで本シリーズでは、人口規模と暮らしやすさの関係を3つの視点から整理しました。
第1章:人口規模と仕事・時給 ― 小都市の限界と東京の別格性
- 小都市では「求人が限られ、時給も低い」という現実。
- 中規模都市でようやく職種が増えるが、賃金は頭打ち。
- 東京は求人数も多様性も別格。
👉 「働きやすさ」という視点で都市を比較した記事です。
🔗 第1章を読む
第2章:都市規模と交通社会 ― 車社会から公共交通社会へ
- 30万人未満は「車社会に最適」で快適。
- 30〜100万人は中途半端で、不便が先に目立つ。
- 100万人以上で公共交通社会が成立し、都会のメリットが勝る。
👉 「交通のあり方」が都市の暮らしやすさを決めることを解き明かしました。
🔗 第2章を読む
第3章:福島市で暮らすリアル ― 快適さと経済的備え
- 福島市は「都会でも田舎でもない、ちょうどよいサイズ」の快適さ。
- しかし仕事の選択肢は少なく、車社会が前提。
- 老後は「年金+資産形成+貯蓄の取り崩し」で生活を支える必要がある。
👉 私自身の体験を交え、福島市に暮らすリアルを描きました。
🔗 第3章を読む
まとめ ― 都市の大きさで変わる暮らし方
- 働くなら東京、暮らすならコンパクト都市。
- 交通は30万人か100万人かが分岐点。
- 快適に暮らすには経済的備えが不可欠。
👉 この3つを理解すれば、自分に合った「住む場所」「働く場所」「暮らし方」が見えてきます。
関連リンク
- 第1章:人口規模と仕事・時給 ― 小都市の限界と東京の別格性
- 第2章:都市規模と交通社会 ― 車社会から公共交通社会へ
- 第3章:福島市で暮らすリアル ― 快適さと経済的備え
- 総集編:人口規模と暮らしやすさ ― 3つの視点から考える日本の都市

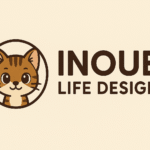
コメント